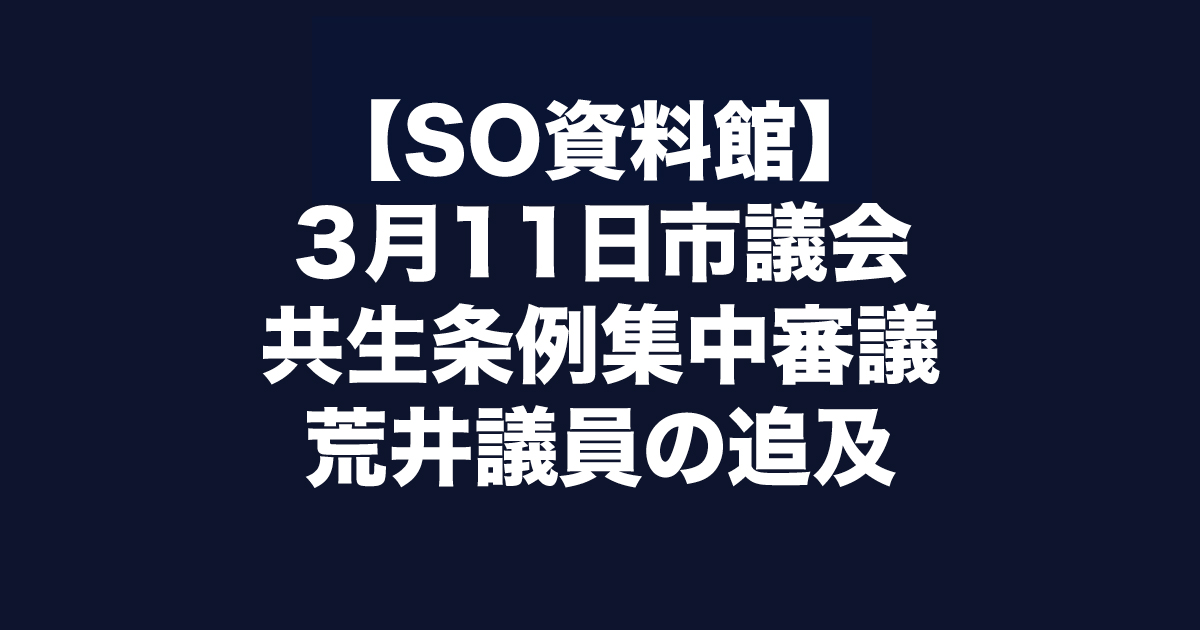なぜ「宣言」ではダメなのか
荒井委員
私は、先般の代表質問、全国47都道府県、他都市の関連条例、検討委員会の議事録パブリックコメントの結果を踏まえまして、会派を代表し、「札幌市、誰もがつながりあう共生のまちづくり条例案」に対して真っ向から反対する立場で質問をさせていただきます。
市長は先般代表質問において、小竹議員、そして私の質問に対し、先ほどの各委員の先生からもお話がありましたが、海外人材を呼び込むため、本条例は必要だという回答と認識をしております。
しかしながら全5回の検討委員会の議事録を拝見すると、海外高機能人材の話題に関しては、一度触れただけで、具体的にどうやって呼び込むのか、このような話もなく議題にすら上がっておりません。
ユニバーサル提供推進委員会の議事録を読み込み、委員の主観的ご意見や体験談ばかりで、客観的な論証または有識者の各条例を比較意見、懸念点などについては全くもって触れられておりません。
例えばですが、各委員の方がおっしゃられたのは、オーストラリアに行って、介護の必要とするワンちゃんを連れてバスに乗ったところ、乗客の方から大変クレーム、批判の声を受けたですとか、また、その他ですね、日本でクレジットカード決済を海外人の方がされたいところで、店員が間違って後ろの方に渡してしまった。このような事案に関しては話し合いですとか、理解があまりにも少ない。
まさに個別の事案ばかりが取り上げられまして、実際にグリーントランスフォーメーションと高機能人材を呼び込むためには、どのような観点で呼び込むような議題は全くもって私にとっては見出すことはできませんでした。
では、本条例は一体どのような性質を持つ条例案でしょうか。
私は、本日この場に立つに当たりまして、一般財団法人地方自治研究機構に発表されております「性の多様性に関する条例」97本、「外国人に関する条例」10本、「障害者差別解消法に関する条例」145本、「人権尊重と差別の解消に関する条例」18本、全てを調べあげて比較検討をさせていただきました。その上で専門家のご意見も踏まえまして質問をさせていただきたいと思います。
札幌市が制定しようとしているこの条例案は、性の多様性、障害をお持ちの方、外国人などを全て差別解消条例に落とし込んだ、先ほど陳情者の方々のご説明がありましたが、人権尊重の条例となっております。
良く言えば、全国でも先駆けた幅広く網羅した条例案。しかしながら、あまりにも何でも詰め込み過ぎな、雑駁すぎる条例のつくりとなっております。
検討委員会の議事録を振り返ってまいりましても、議題の課題は差別と偏見の解消に特化した内容に終始しております。この点につきまして、市長の答弁内容を踏まえまして、札幌市民の皆様のご理解が進むとは私は全く思っておりません。
その上で、他都市の差別解消条例と比較しますと、財政措置が文言として記載しているにもかかわらず、予算がどこにいくのか見出せない。透明性はない。
委員が何回もわたり、再任されることによる所属する関係団体の特定の意見・思想が、市の政策や取り組みに色濃く反映されてしまう懸念があります。
さらには、条例制定が有効に運用されているか、確認するために見直し期間と検証や評価や報告の方法も明記されておりません。
そして、最も重要な日本国憲法の保障する国民の自由、権利を不当に侵害しないと留意しなければならないといった表現の自由等の配慮の文言も全くもって明記をされておりません。
その様々な検討事項を踏まえまして、パブリックコメントや陳情を拝見しますと、札幌市が目指す共生概念は、既に札幌市民憲章に盛り込まれるなどして条例制定は不要との意見が一定数あるとご承知しております。
札幌市は「札幌市平和都市宣言」に代表されるように、地方自治体の意思や主張・方針等を内外に表明する事例もあり、共生社会の実現に向け、市民・事業者の意見を向上する、こういった機運の醸成に当たっては、この「宣言」という形で市として示すことで私は十分こと足りると思っております。
例えば、市長がご説明されましたように、海外の方々を公共人材を呼び込むために条例が必要だというのであれば、それによって企業や市民を啓発することができるというのであれば、ではなぜ、例えばですが、オリンピック開催にあたり、オリンピック開催促進条例ですとか、敬老パス、世代間格差撲滅条例ですとか、そういった理念を掲げれば、国としての政策を、札幌市の政策としても実行することができたのではないかと思っているところでございます。
そこでまず質問ですが、共生社会の実現に向けては、条例ではなく「共生社会推進宣言」などを検討すべきと考えますが、いかがかお伺いします。
山内ユニバーサル推進室長
ユニバーサル推進室長の山内でございます。条例制定時の必要性についてのご質問でございます。
本条例は共生社会の実現に向けて、市・市民・事業者の各主体が連携・協働して具体的な取り組みを進めていくことを目的に制定するものでございます。
このため本条例案では、基本理念・市の責任、市民および事業者の役割、これらを定め、これらを相互に理解認識した上で、誰もが自分事として捉えて取り組みを進めることができるような内容としているところでございます。
加えまして、市が率先して取り組みを進めるという姿勢を対外的に示す観点から、市が行う基本的政策や、推進体制、それから施策の進捗管理等を行うための附属機関の設置、これらを定めているところでございます。
一方、宣言や札幌市民憲章、こういったものはそれぞれ地方自治体の意志等、あるいは市民の目標や規範などを示すに伴う留まるものであり、市・市民事業者が連携協働した具体的な取り組みの推進という観点からも条例の制定が最適と考えているところと考えております。
思想と言論の自由を守る歯止め条項が必要だ
荒井委員
答弁の方、本当にありがとうございます。とは言うもののですね。全5回の検討委員会の議事録振り返りましても、第3回の議事録でございますが、座長自らこのような発言をしております。
「共生社会は多様性という言葉に対しまして、反対するというような流れも社会の中で、起きているときとひしひしと感じることがあります。ポリコレ批判ということもありますし、トランプ現象ということもそうですが、アメリカもヨーロッパでも立場の違う人たちを排除することのような圧力も一方でじわじわと世界情勢としては起きているように感じることです。その中で共生社会の実現に向けた条例を作るということには、大変な覚悟は要るものだろうと思います」
これは本当にこの発言、座長自らがされている時点で、私は本条例案に対して全国で例を見ない政治的にリベラル色の強い、革新的、急進的すぎるイデオロギーに富んだ、そしてなおかつ歯止めの利かない条例だと判断せざるを得ません。
私自身、差別に関しては、全くもって反対ではございます。しかしながら、差別を是正するための政策において、様々なこれからの事象を申し上げますが、懸念点も、海外でなく日本国内で起こっても確かでございます。
代表質問で申し上げましたように、実際、検討委員会の資料として障害者のためのインフラ施設ですとか、海外の人のためのインフラ設備等も含め、札幌市は予算を使う政策を実施実行している限り、本条例は成功するのか、結果が伴わないかということは、逆に検討委員会の資料をもってしても証明されたのであります。
何を言いたいかと言えば、条例を制定してから政策を移すことではなく、もう実際に札幌市で現在進行形で予算が割かれ、様々な政策が実行されていることは、資料に記載されているのであります。
本条例の代表質問でご指摘させていただきましたが、アファマーティブアクション=積極的格差是正措置。これは1960年70年代ですね、黒人の方々に対する非情なシビルアクト (civil act)、差別等が大変蔓延した結果を踏まえて、アメリカで制定されたものでございますが、約10年ほど前でございますが、代表質問を触れました通り、連邦裁判所で違憲判決が出ております。
本条例に関しまして、私はそういったことも含めまして、やはり条例素案内容に鑑み、DEI条例そのものであると判断いたしました。
DEI条例に関しましては、先ほど申し上げましたが、ヨーロッパやアメリカの当事者の立場から差別を助長する政策だということで、様々に今現在、廃止をされておりますし、時代に逆行した本条例を施行することは、今後、国際都市札幌を目指す上で、弊害になることは間違いなく、市長がおっしゃる海外の方々が本当に望んでいるのか、私には到底思えません。
また、金融都市として名高いロンドン・ニューヨーク・香港・シンガポール・イギリスの例をとって見ましても、金融都市実現のために、まずははじめに条例を制定したから成功したという事例は聞いたことはございません。
先ほど申し上げましたが、国際情勢の流れを考えてみましても、そもそも海外の方が条例制定を本当に望んでいるか、という正しい検証が必要であると思います。
その上で議事録を拝見するに当たって、座長自ら本条例を施行するにあたり、一番最後の検討委員会第5回ですね。本条例は、民主主義を守るためにも、制定が必要だというような意見をされておりますが、本条例を施行するには、それ相当な覚悟が必要だといったことを発言してる点は、残念ながら大変イデオロギー色が強い条例素案というふうに意識を判断せざるを得ません。
その上で私の体験から申し上げますと、アメリカ生活を振り返った身の体験として、本条例案を施行すれば、特定の価値観による差別が横行する可能性が非常に高いという視点をご指摘させていただきます。
これは私の思いではなく、先ほどの国際情勢を鑑み、また約2000件を超えるパブリックコメントの市民の反対の声からも間違いないと言い切れるものであります。
市長は様々な議論や意見を取り入れるため本条例が必要だと小竹議員の質問に対してご回答されました。しかしこの条例を施行した結果、議論の必要な事案が人権の名のもとに一的に押し付けられ、差別と断じる可能性を大いにはらんでいるのであります。
障害者差別解消法の改正に伴いまして、政府により詳しくその範囲、または例を示すガイドラインが発表されております。しかしながら本条例案は、先ほど申し上げた通り、いろんな多様性をざっくばらんに包括した条例であるがために、差別や偏見の定義がないこと。市民や事業者の不安を呼び込んでいると言えます。
そもそも札幌市は、差別、偏見の定義を明確にしておらず、個別の事案ごとに具体的な場面や状況に応じて、総合的、客観的に判断されるものと、パブリックコメントの質問に対して述べております。
では、どういった方々が、差別、偏見、判断されるのを例として判断されると想定されるでしょうか?
本条例素案に関係した検討委員の皆様は、その立場に置かれることは想像に難くなく、個別の事案、その個人が評価することは思想信条の自由を奪うことしかありません。そういった懸念があるからこそ、11月にあるだけのパブリックコメントが集まったのではないでしょうか?
であるならば、心のバリアフリーに関して評価基準を設けるべきでありますし、ましてや罰則規定などを設けるべきではありません。
わが会派の代表質問においては、本条例に関して市長から、本条例は特定の団体や個人と他を比較して、特別に優遇するとの根拠はない、といった答弁がありました。
しかしながら、改めまして検討委員の議事録を振り返ってみますと、このような発言が度々ございます。「差別禁止規定や罰則がないから実効性がないものになる」「行政には積極的な対応を恐れないで欲しい」「条例が出た後に実効性を伴う担保はどうするかが重要」といったご意見がございます。
さきほどの答弁について理解したところでございますが、条例を制定したとしても、今後市長の思いが異なり、条例制定の数年後に特定の団体や個人を優遇する政策が実施されたり、条例等で罰則が今後設定されるものはないかと危惧する声が上がっているのは確かであります。
そこで質問ですが、条例を制定するのであれば、やはり本条例案、特定の団体や個人を優遇にすることを禁止する規定や罰則を今後を設けないこととする規定を追加して、条例上明記すべきだと考えますが、市のお考えを後開示願います。
山内室長
条例案の修正等でございました。まず本条例案は共生社会の実現に向けた理念条例であり、規制条例でないことから罰則等は設けていないところがございます。
また本条例に基づき、今後市長が定める規則等においても罰則を設定する考えはございません。
加えまして繰り返しになりますけれども、本条例は個人の価値観や考え方には違いがあることを前提といたしまして、「誰もが当事者」の考え方のもとで設定を目指すものであり、特定の団体や個人を他と比較して特別に優遇するなどといった根拠になるものではないことから、条例案の修正は必要ないものと考えております。
それでも自由を奪いかねず、容認できない
荒井委員
ご答弁ありがとうございます。しかしながら、条例を制定するということは、ある意味で市民の思想信条を縛るおそれがあるものであります。
この件に関して、私は十分な審議がなされているとは全く思っておりません。その上で、私自身の調査および条例に対する認識を客観的な事象の論証を持っ意見を申し上げてまいりましたが、本条例について専門家の方々に意見を賜りました。
東京都新宿区中野宏和弁護士を始め、杉山光彦弁護士から、子供たちへの特定思想刷り込みの懸念、DEIを推進する国において多様性の研修の結果、効果が学術的に成功したと検証された事例が見つからない。第8条第2号、条例措置を講じることに対し、住民から行政訴訟が提起される懸念。
千葉県は相談窓口を設置し、昨年8月から知事の肝煎で8月からLGBTQといった性的少数者の方々を対象に、電話の相談受付を始めたが、半年間に受けた相談件数は電話で10件、メールで10件であったにもかかわらず、翌年度予算を10倍とし、他方から問題視する声が上がりました。
多文化共生を進めてきたドイツを始めとした他国、治安悪化の失敗例等々を鑑み、その上で他の自治体条例を参考とするなら、「相模原市人権尊重のまちづくり条例」愛知県の「人権尊重の社会づくり条例」、沖縄県「差別のない社会づくり条例」この3条例に関し、憲法上の表現の自由が盛り込まれています。
本条例を通すことは、札幌市民の思想・信条を奪いかねず、到底容認できるものではないというようなご意見をいただいた限りであります。
そこで最後に市長にお伺いしたいと思います。条例案に懸念を有する立場からは、札幌市は共生社会の実現という名のもとに姿勢を強化し、表現の自由その他日本国憲法の保障する国民の自由および権利を不当に侵害する方向に進んでしまうんじゃないかと大変危惧しているところでございます。
この点、愛知県で本条例に類似する人権尊重の条例において、この条文内に表現の自由その他日本国憲法の保障する国民の自由および権利を不当に侵害しないよう留意しなければならないとする旨の規定を設けているところです。
そこで質問ですが、憲法が保障する国民の自由および権利を不当に侵害しないよう、市としてこの点をどのように担保していくお考えなのか、市長のお考えをお聞かせください。
秋元市長
憲法との関係でお話しをいただきましたけれども、これ冒頭の答弁の中で申し上げました。他の自治体でそういった表現条文があるのは規制条例である。何かを規制するか故にそれが行き過ぎないようにするというブレーキをかけた条文です。
繰り返しになりますが、今回提案をさせていただいては、なんかの規制をするというものではございませんで、いろいろな、これまで様々なご答弁、質疑の中で、生きづらさを感じられている方、一定程度いらっしゃる。そういった方々の生きずさを解消していく。
そして高度人材、外国からの高度人材にかなり特化したお話いただいてますけど、外国市民の方が増えることの懸念ということに対して、そういうマイナス面だけではなくて、札幌として、北海道としてそういう人材を受け入れていく多様性、いわゆる多様な人材を受け入れていかなければいけないんだということを少し強調そして申し上げました。
この条例の目的はそのことだけにあるわけではない。るる質疑があったように、いろいろな差別、あるいは偏見を感じそういった方々の生きずらさを解消して、1人1人が個人として尊重されれていく社会を作っていこう。そういう理念を共有していくというところで、ご理解をいただきたいと思います。
という意味では、まさにそういうことを共有していきましょうということで、何かを規制して、特定の考えを否定、押し付ける、こういうものではない。ということでありますので、それを担保するということは、まさにこの条例の立て付けとして、そういった考え方も含めた、基本的人権を進めて尊重していくことが、大前提のもと行うものである、ということでご理解いただきたいと思います。
短すぎる。もっと時間をかけるべきだ。
荒井委員
ご答弁、本当にありがとうございます。しかしですね、市長が高機能人材の方々をお呼びしまして、金融市場を盛りあげるために人材が必要だと言うことに関しまして、私くしもGX経済を推進させる立場で評価しているところでございますが、やはり市長のご説明と、委員会の議事録の内容はまったく、180度違う。市民からこういう声は当然あるものでありますし、市民の理解は本当に進んだと考えることはできません。
この短期間においても、これだけ不安材料が続出しているのは……先日の代表質問からですね、市民の方々から意見をいただきまして、本日の質問等させて抱いておりますが、やはり不安なこと点だらけでございまして、本定例会の議案採決で可否を問うのは、あまりにも審議時間が短すぎると感じております。
この条例制定は時期早々であり、醸成を図る期間はもっと必要ではないでしょうか?
条例制定は段階を経て行うべきだと考えます。現段階で一気に条例制定を強行するというのではなく、「共生社会の宣言」などをやはり検討し、機運の醸成を図った上で条例制定することが適切だったと考えます。
最後に、私の意見は、おそらくこの議会のマイノリティでございます。ぜひ私のご意見を踏まえまして、少数意見を尊重していただいた上で、定例会において議決ですとか、条例制定に当たり、十分な審議時間を持って検討していただきたいと切に願っております。
その上で、これも指摘させていただきたいんですけども、子供への教育ということを取り上げますと、条例制定後、子どもへの教育を実施することになり、子供にもたらす何らかの心の準備もなく、教育を受けることとなり、不安等の感情を有することになりかねません。共生社会を考えるにあたって、ここはこうじゃないという発言がありました。
だからこそ、拙速なことは危険をはらんでいると考えるわけですが、誤った正義感での差別の説明は、実際に、本当に差別されてる方の差別を呼び込む可能性があるということを十分に指摘させていただきたいと思います。
例えば、理念法でございますけども、悪名高い大正期の治安維持法なんかは、当時無政府主義者を取り締まるための、議会で大変紛糾したものでございますが、当時は評価され、後に罰則規定を設けたものでございます。
教教育勅語も広くは理念法のような位置付けでして、国家に忠義を尽くしなさいと戦争批判の上で上がっていますが、内容はお父さんお母さんを敬いなさい。兄弟夫婦皆仲良くしなさいと言った道徳的な内容で当時国民市民から大歓喜を持って受け入れられたものであります。
私は何を申し上げたいかと申し上げますと、当時は評価された法同様にこの理念条例も後に全く評価されない恐れがあるという事です。
市長私は2年近く一緒に働かせて頂き、政治家としての市長を尊敬しておりますし、理想を掲げた上で現実を見据えた政治家だと思います。それだけに後に晩節を汚す恐れのあるような理念条例を敢えて可決すべきでは無いし、慎重になるべきです。
その上で大変恐縮ですが、私はやはりこういった諸事情の懸念事項を踏まえまして、市民の皆さんが理解を踏まえた上で、条例の制定にこぎつけるよう考えていただきたいと切に思いまして、大変長くなりましたが私の質疑を終わらせていただきます。ありがとうございます。