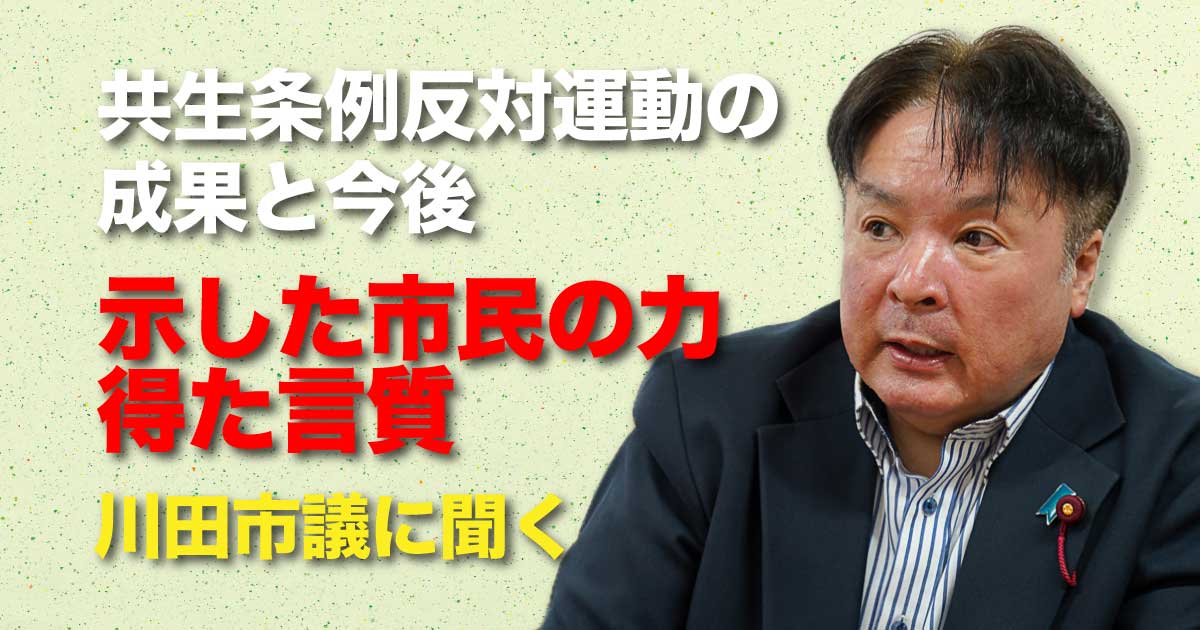平成7年3月28日に閉会した札幌市議会第1回定例会で「札幌市誰もがつながり合う共生のまちづくり条例」(共生条例)は可決成立し、4月1日から施行されています。「共生社会」を目指す理念条例ですが、かつてない規模で反対の声が上がりました。この条例の懸念を伝えるために立ち上げた当サイトですが、条例制定を受けて運動の先頭に立った川田匡桐(ただひさ)市議へのインタビューを交え、今後に向けて条例反対の取り組みを振り返ります。
市民の声を塊として示した経験
共生条例の本質は、社会をマイノリティとマジョリティに分断した上で、マイノリティが生きやすい社会はマジョリティも生きやすいという理屈により、マイノリティの目線で社会を書き換えるものです。
こうした理念=イデオロギーは、少数者を絶対化するもので、最大多数の最大幸福を目指す民主主義の本旨と相容れません。このために外国人移民を警戒する立場、性的少数者の立場、歴史や文化を尊重する立場など、多くの立場から反対の声が上がりました。
一方で、市民に対する罰則や規制が設けられておらず、「差別や偏見のない社会」「誰もが個性や能力が尊重される社会」など耳当たりのよい、反対の難しい言葉で覆われた条例であるために、この条例の本質に気づくことに遅れてしまいました。
結果として条例の成立を許すことになりましたが、反対が9割を超える1014人からの2068件のパブリックコメント、108件の反対陳情などが寄せられました。
罰則条項など明解な論点がないものであったとしても、理念=イデオロギーに対して、これを市民社会の脅威と認識し、反対の声を挙げ、市民の声を塊として市に示すことができたのは、経験としても大きな成果でした。
運動がなければ得られなかった成果としての「言質」
多数の陳情が寄せられたことで、市議会では条例をめぐって論戦が行われました。ここで示された「言質」は、反対運動がなければ得られなかったものであり、今後、私たちがこの条例がもたらすものと戦っていくための武器となるものです。
それらには次のようなものがあります。
- 本条例に基づいて、市民や事業者に特定の考え方やその対応、価値観を押し付けたり、強要したりしません。
- 本条例に基づいて、入札制度を変更する考えはありません。
- 条例の対象を一部の方に限定しません。
- 本条例に基づき、今後市長が定める規則等においても罰則を設定する考えはございません。
- 本条例に基づいて、特定の団体や個人を他と比較して特別に優遇することはありません。
- 本条例に基づく個別施策や事業の実施に当たっては、個々にその必要性を精査した上で実施等の判断を適切に行い、その都度議会に諮ります。
- 本条例に基づく個別施策や事業の実施に当たっては、客観性のある評価指標を設定して、毎年度の効果検証によって、その立案や見直しを適時行います。
- 本条例に基づいて、具体の事例に関する差別や偏見の該当の有無について、何らかの認定や判断といったことを行うことはいたしません。
- 札幌市誰もがつながり合う共生のまちづくり委員会の委員の人選については、条例に反対や疑問を呈した市民の登用が重要だと認識します。
- 条例制定をひとつのきっかけに、条例に反対や疑問を呈した市民との更なる対話を重ねていきます。この条例に対する理解、あるいは誤解に対しては、きちんと説明してまいります。
川田匡桐市議インタビュー

今回は本当に市民の力!
市民の力がなかったら一人では無理でした
共生条例ですが、先生は早くからこの条例の問題について警鐘を鳴らしていました。いつ頃から危険を認識していたのでしょうか?
(令和5年統一地方)選挙の直後です。初めはわからなかったんです。
秋元市長の選挙公約に「共生条例の実現」とありましたね。
市長を応援する気はなかったから〝分からない〟というよりも関心がなかったんです。後になって他の議員から聞いて〝なんだ!これは?〟ということで興味を持ったというか、直感的に〝危ない〟と思ったんですよ。
それでも具体的な事象としてどうなるのかという部分は、やはり見えてこなかった。だから気がつくのが本当に遅かったということなんです。
怪しいな、という疑いが具体的な危険に変わっていったのは、いつくらいからですか?
だんだんと体系的に見えてきたのは、やはり去年の春ぐらいからですね。在日朝鮮人や中国人の話だけでなく、難民移民、性的マイノリティー……そういったものもでてきた。
そもそも共生条例のはじまりは「札幌市まちづくり戦略ビジョン」(令和4年)からです。戦略ビジョンは〝札幌をDEIのまちにしよう〟ということだったとすれば、共生条例はその最終章、仕上げに入っていく段階です。
しかし、初めはそのことを僕も体系的には理解できていなかった。結局モグラ叩きをしていただけです。モグラの巣を抑えていなかったという反省があります。
「札幌市まちづくり戦略ビジョン」を見ましたが、ユニバーサル、ウエルネス、スマート……本当にカタカナだらけですよね。
今の憲法と同じです。GHQが作った憲法だから変な日本語表記があったりするのと同じ。共生条例も結局アメリカでやってきたことを日本に押しつけるといこうことでは同じです。秋元市長は、それをそのまま受け継いでしまったということです。
でも、そういうことが見えてきたのは去年の春ぐらいから。何が具体的にどう怪しいのか? 具体的な事象としてどうなのか? という部分は、なかなか見えてきませんでした。
条例を検討したユニバーサル検討委員会の議事録を読むと、保守派の反発——バックフラッシュと彼らは呼んでいますが——を警戒して、できるだけ当たり障りのない言葉に言い換えたとユニバーサル推進室長が言っていました。たしかに表面的に条文を読むだけでは何が問題か分かりにくいですよね。
僕の支援者と勉強会を開いたんですが、最初は全く分からなかったんです。「いいことが書いてあるでしょう」と。「いやいや、いいことじゃないです」と。要するに善良な人たちを騙すように書いてあるわけです。そういった言葉尻をつくっているだけなんです。これには怒りを覚えました。
風向きが変わったのはいつからでしょうか?
やはり、皆さんがパブリックコメントをやってからですよ。それとトランプさんの大統領選挙が大きかったですね。去年の3月くらいから大統領選挙の予備選挙が始まりました。ちょうどその頃に札幌では同性婚訴訟の高裁としての初めての判断が示されました。DEI、同性婚など、トランプさんの主張がマスコミにも取り上げられ、ネットでも話題になりましたよね。あれは大きかったと思いますよ。
アメリカでの大統領選を通して、漠然としていたものの大変さとか、危なさというものが、浮き彫りになっていきました。そして選挙が終盤に近づくにつれ、その危なさが保守系の人たちに浸透し始めたということですね。
共生条例パブリックコメントの締め切りは11月末、アメリカ大統領選の投票日は11月5日。たしかに大きな影響を与えましたね。
1月20日の大統領就任演説で「アメリカは今日から男と女しかいない」と言ったことも含めて、マスコミはトランプ批判としてクローズアップしたわけですが、今やマスコミが言うことの反対が正しいんだと捉える現象がありますよね。神戸の知事選挙、名古屋の市長選挙しかりです。
世の中がだんだんそうなってきた中で、マスコミがトランプさんの主張を否定的に紹介したことで、〝そういうことなんだ〟と捉える人が増えていきました。「トランプ革命」と呼ばれますが、遅かったにせよ、トランプ革命にとにかく乗ったことによって〝これは問題のあるものだ〟という認識をもつことができたのは大きかったですね。
3月議会で制定して4月1日から施行というスケジュールを見ても、市は反対の声が上がることを全く想定していなかったと思いますね。
そう思いますよ。反対があっても川田一人だけだろうと(笑)
だから、今回は本当に市民の力ですよ。ぼくが煽ったかのように言う者もいたので「俺にそんなに影響力があるのか!」と言ったら、何も言わなくなりました。
だって、ひとつだけの意見ではありませんから。(条例の対象には)外国人が入っていれば、障がい者も入っている。何かは特定していない。それで「(煽っているのは)どこの誰なんだ———」と、とにかく問い詰めていく。すると何も言わなくなった。
結果的にパブリックコメントは2000件を超えました。
市は慌てたと思いますよ。こんなに来るとは思わなかったでしょう。それで市は僕に「市外からたくさん来ていますよ」と、ひたすら「市外の意見だ」と言って逃げようとするわけです。そこでぼくは「市内からも来ているはずだ。それは何件で、今までのパブリックコメントの何倍なんだ」と聞き返しました。
そして2月13日から市議会の第1回定例会が始まります。パブリックコメントの高まりを受けて陳情も160件を超えました。最終的に不適切なものをはぶいて108件となりましたね。
普通はひとつの定例会で陳情は数件です。ですから来た陳状が委員会で取り上げられないということはほとんどない。ただオリンピック招致を巡っては相当数の陳情が来たので、一昨年から2つ以上の会派が同意したものに限って委員会に上げることになりましたから、これからは取り上げられない陳情は増えると思います。
それでも今まで一つの案件に対して陳情が100件以上来たことは無いんです。僕だって10件くらいかなと思っていたんですから。この100件によって議会事務局をはじめとして(共生条例について)僕の言っていることが〝やばい〟ことなんじゃないかと認識したと思いますね。この〝やばい〟っていうのは、僕の考えに賛同して〝やばい〟と思っているのではなくて、この案件に触れると〝まずいことになるんだな〟ということですが……。
陳情は第一予算特別委員会に付託されました。本来ならば総務委員会に回されるべきものだと聞きましたが?
そうです。それなのに予算委員会に行ったのは、要するに何も審理しないで通そうと思っていたんです。条例だけを浮き彫りにさせたくなかったんですね。でも結局浮き彫りにせざるを得なくなった。だから100件という数は重たいんです。1つ2つの陳情だったら無視するつもりだったと思いますね。結果的に条例を予算案から切り離しての審議と採決になりましたから、100件超えはきわめて大きかったですね。
3月11日の第一予算特別委員会で集中審議が行われました。多くの質疑応答がありましたが、陳情がなければ本来はなかった答弁を引き出したかたちですね。
僕が今回の成果だったと思うのは、議会の質疑応答がネットで流せたということです。彼らにとって自分たちの質疑が世に出ることはもっとも嫌がることですから。
議会答弁を通して得られた「言質」はすべて成果であると。
そうですが、彼らは簡単に引っくり返しますよ。彼らにとっては議会なんてどうでもいいんですから。ですから1か月に1回は財政課とか、そういったところに市民の皆さんから「あれはどうなった」と言って欲しいんです。僕もやります。
11日の審議では、ユニバーサル検討委員会では一言もなかったGX特区を市長が持ち出してきましたね。GX特区の高度金融人材を受け入れるために共生条例が必要であるかのような言い方でした。
最後の最後になって問題の本質をやっと出してきたということなんです。市長懇談会の時に「いや、(GXは)関係ない」と言っていたんですよ。(条例に対する)財政措置もそうです。当初は「(理念条例だから予算措置を)しない」と言っていたんです。しかし、私は「絶対やる」と思っていたんですが、案の定出てきた。
GX特区、すなわちグリーン・トランスメーションは、バイデン民主党のグリーン・ニューディールをそのまま持ってきたものですが、トランプさんは1月20日の大統領就任式のときに、バイデンのグリーン・ニューディールを破棄しています。それなのに彼らはGX特区の説明会を1月30日にニューヨークでやっているわけです。40人くらい来たと言っていますが、アメリカ民主党と国際金融資本、これが後ろについている、そう思っているんです。これが(共生条例の)本質なんですよ。
11日の審議では他に、共生条例の実効性を担保するための「共生のまちづくり委員会」の人選について「反対派も入れろ」という川田先生の追及に対して市長は「考慮する」と言いましたね。
最後に市長からそういう話が出たのは大きかったかもしれないですね。
それでも彼らは強行しようと思っていますよ。彼らを、平和を愛する一般国民の仲間だと思っちゃいけないんです。彼らは我々日本人を憎んでいる。日本人であることが心の傷として、その傷が憎しみとして残っているような、そういう連中なんです。
僕たちは優しいし、普通の日本人として信頼をいただくように真面目に生きてきたわけです。本当にいい人なんですよね。我々日本人というのは。だからこそ彼らはそこを突いてくるわけですよ。
彼らを、我々と同じ心を持っているはずだという感覚は本当にやめた方がいいと思う。そうした感覚と決別できるか、できないかが今後我々の勝利の要になっていくと思います。これからが本当の勝負です。
3月28日の本会議では、共生条例について8名が反対、1人が棄権、あわせて9名が不賛成の意思表示をしました。どう評価されますか?
満足はしていませんが、まあまあかな———。条例は通ってしまったけれども、一太刀浴びせることはできましたから。
正直言って、ここまで来られるかどうかというのは、2月後半から3月上旬はまったく分からなかったんです。大きな声を出しあう場面もあったんですよ。
僕は、党議拘束があってもなくても「反対」とみんなに言っていました。市長にも直接「僕は反対します」と言いました。議会で党議拘束に逆らうと除名されることもあります。後援会の役員会で「今そういう状態です。皆さんどうしますか?」と投げかけたところ、「そうなっても全力で応援するから、意志を貫いてください」と全会一致でした。そのことにとても感謝しています。
札幌市の民生分野の基本条例にもなるこの条例について、党議拘束をかけないのは自民党としても大きな判断でしたね。党議拘束があればほぼほぼ全会一致もあったわけですから。先生の出演する「チャンネル桜北海道」で党議拘束が外れたことを知りましたが、収録は3月27日で採決の前日。最後の最後まで攻防が続いたんですね。
僕は言われましたよ。「除名されてもいいのか」と。こう言いました。「いやいや、自民党除名はおかしいでしょう。僕がこの会派室に1人残り、みんながいなくなることがあっても僕が出ることはない」。「(条例に賛成する)みなさんが立憲民主党に行けばいいんじゃないですか」。これはずっと言い続けました。
出ていくのは賛成する者たちだ!———すごいですね。
会派としては半数以上が賛同していたので「賛成」となりましたが、党議拘束について多数決を取ったところ5人ほどしか手を挙げなかったんです。それは「チャンネル桜」の収録の日、採決の前日でした。条例に賛成しても党議拘束については、さすがにおいそれと手を上げられなかったんですよ。
議員個々に電話やメール、ファクスがかなり来ていたようで、「まいったよ」というので、こう言いました。「条例に反対すると推進したい勢力から狙われるだろう。でも賛成しても狙われる。この世界、どちら側からか必ず狙われるんだから、どちらを選ぶのか、よくよく考えてもらいたい」と。
今回は本当に市民の力です。これこそ市民の力だと思いました。市民の力がなかったら僕一人では到底無理でした。ここまで来ることはできなかった。
これまでの札幌市議会では一つの案件に対して双方から狙われることはなかったんですね。さて結果的に議会では定数の13%をこえる非賛成が示されたわけです。この条例を全会一致で成立させるのと、無視できない数の反対があることを示すのでは、とても大きな違いがありますね。
今回マスコミも冷静に「反対もいた中で可決された」と書いてくれました。読売は特に「保守系の反対」ということを書いてくれたから、自民党会派が多い市町村からすると、〝保守系が反対するような条例なんだ〟という認識を持たせたというのは大きいと思いますね。
それでも市は、この条例を盾にいろんなことを強行しようと思っていますよ。暗い部屋で明かりをつけなくても、だんだんと目が慣れて見えてくる場面ってあるじゃないですか? 今保守の一部がようやくそういう段階になったんだと思います。だから一般の人たちはまだまだ分からない。そこに乗じて市はいろんなことをやってくると思います。
われわれ市民としては今後どうしていくべきでしょうか?
やはり、ありとあらゆる事象に対して、市や議会に対し意見を述べていくことですね。もちろんネットなどに書き込むのも一つなんですけど、それだけではなく、やはり議会や行政に対して、文章にして意見を直接もっていく、ちゃんと住所と名前を表したかたちで示していくことは大事です。
条例は通ってしまいましたが、それでも今回〝自分たちが動けば効果を出せるんだ〟ということが分かったのは、とても大きかったと思います。